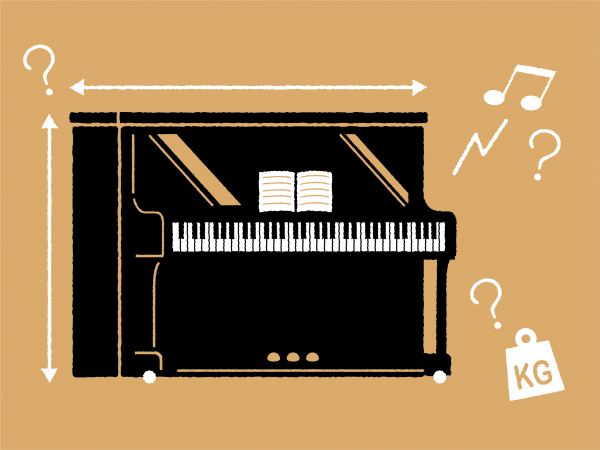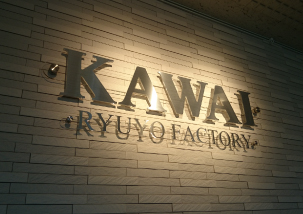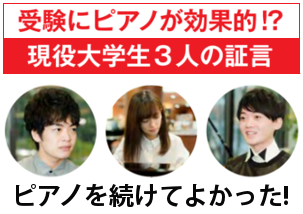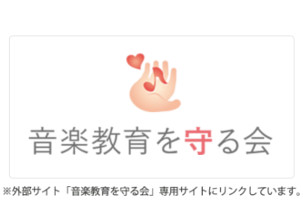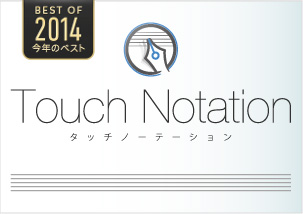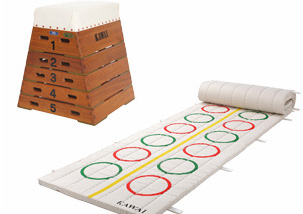現在、国際医療福祉大学大学院 副大学院長・同大精神医療統括教授を務められ、スポーツ精神医学の第一人者としてさまざまなアスリートのサポートにあたるとともに、近年、浜松国際ピアノアカデミーなどで音楽家のパフォーマンスとメンタルマネジメントに関する講演も行っている伊豫雅臣(いよまさおみ)先生に、ピアノ奏者がパフォーマンスの向上を目指すにあたって科学的にどうアプローチしたら良いのか、お話を伺いました。
取材・文:飯田有抄
ピアノと精神医学:
ピアノの上達に効果的な練習とは
―――伊豫先生は音楽家の心と体のサポートにまつわる「パフォーミングアーツメディスン(Performing Arts Medicine; PAM)」という分野の研究を取り入れ、音楽大学の学生や、浜松国際アカデミーでの講演をなさっておられます。これはどのような研究なのでしょうか。
パフォーミングアーツメディスンは、芸術家の怪我や治療を専門とする分野です。スポーツではよく知られていますが、「イップス」と呼ばれる、急に体が思うように動かなくなる症状があります。これは、ピアニストなど音楽家にも見られ、プロでも引退の原因となることがあります。パフォーマンス時に脳と体がうまく連携しない状態で、そうした症状に向き合う分野でもあります。
―――ピアノの上達において、精神医学の観点からは、どのようなトレーニングが重要なのでしょうか?
興味深い研究結果があります。熟練したピアニストの場合、実際にピアノを弾くことと、演奏された音楽を聴くことを比較すると、熟練者は「聴く」ことによってレベルが向上することが分かりました。楽譜を見ながら音楽を聴くことで、実際に弾くよりもパフォーマンスが向上するという結果が出ています。
具体的な研究では、被験者が「楽譜を見ながら演奏を聴くグループ」「楽譜を見ながら自分で弾くグループ」「楽譜を見るだけのグループ」を比較しました。最もパフォーマンスレベルが向上したのは「演奏を聴くグループ」で、次が「楽譜を見るだけのグループ」でした。意外にも、「楽譜を見ながら弾くグループ」の成果が最も低かったのです。
―――なぜ聴くことが、それほど効果的なのでしょうか?
脳科学的な観点から説明すると、音楽を「聴く」ことに集中している時は、聴覚野が強く反応します。しかし、そこに「弾く」動作も加えると、脳の活動が全般に広がってしまい、学習としては曖昧なものになってしまいます。「聴く」という特定のことに集中してイメージすることで、より効果的な「自動化」につながるのです。
―――「自動化」とは何でしょうか?
反復練習により、意識しなくても体が動くようになる状態が「自動化」です。脳から筋肉・体の動きを司る基底核という部分に運動記憶が蓄積されます。基底核からの運動記憶はほぼ永続的で、いったん自転車に乗れるようになったら、特に何も考えなくてもずっと乗り方を覚えているのと同じように、一度身につけた技術は長期間経っても失われません。
―――基底核から一次運動野に指示を出す「自動化」には、年齢的なリミットなどはあるのでしょうか?
一般的には12〜14歳頃までと言われますが、年齢が上がっても自動化は可能です。スポーツの場合、30歳を過ぎたプロの選手が更に上達することもあります。基本的には子どものほうが習得が早いですが、ある程度の年齢以降でも、時間はかかるかもしれませんが、自動化や上達することは可能です。
 世界的なプロピアニストの育成を目的として1996年からスタートしたピアノアカデミー:浜松国際ピアノアカデミーにて
世界的なプロピアニストの育成を目的として1996年からスタートしたピアノアカデミー:浜松国際ピアノアカデミーにて
イメージトレーニングの重要性
―――たとえば、強く集中するような体験が、上達を促すことはあるでしょうか。たとえば、ステージ上での本番を経験することで、上達することがあるように思います。
そうですね、集中しきったときの「ゾーン」という状態があると思います。不安がなくなり、全て思った通りに体が動き、周りがゆっくり見えるような状態です。そうしたゾーンに入るためには、「達成可能なチャレンジ」を続け、「モチベーションの向上」を維持することが重要です。モチベーション向上には自分の成功体験が大切で、うまくできたことをしっかり受け止め、それをもとにステップアップしていく自己効力感が「もっとできるかも」という期待値につながります。
まず上手くできたところを認識し、次に修正点に目を向ける。修正することでさらに上達できると考える。これを「PNP(ポジティブ・ネガティブ・ポジティブ)法」と呼びます。
失敗ばかりをイメージしていると、本番で失敗のイメージが浮かんでしまい、不安や恐怖の反応として固まったり、頭が真っ白になったりしてしまいます。
―――スポーツではイメージトレーニングが重要とされていますが、演奏においても効果が高いのですね。
スポーツでのイメージトレーニングから着想を得て、音楽家も同様の手法を取り入れることは非常に有効です。ピアニストは指や腱の故障に悩まされがちですが、練習時間の一部をイメージトレーニングに充てることで、身体への負担を軽減しながら効果的な上達が可能になります。
練習が足りないと感じるなら、イメージトレーニングを活用すればよいのです。あくまで成功をイメージします。本番で失敗してしまうかもしれない、という不安・恐怖のイメージを重ねてしまうと、実際に体が固まったり腰が引けたりする。失敗イメージを固定化させないことが大切です。「失敗するかも」という思いは「予言」ではありません。「気をつけて頑張ろう」というアドバイスだと受け止めるとよいでしょう。不安に無理に打ち勝とうとするのではなく、受け流して「今ここ」に集中する、マインドフルネスなどを取り入れるのもよいですね。
ピアノが「つらい」と感じたら…
―――ピアノを続けていく中では、「つらい」と感じることもあると思います。どのような対処法があるでしょうか。
「つらい」と感じるのは、自分のレベルに対して高すぎる目標を設定している可能性があります。がんばれば達成できる目標を掲げ、その達成を繰り返していくことが大事です。スモールサクセスの積み重ねですね。成功できることは嬉しいので、さらに上を目指そうという気持ちを維持できます。
なお、目標には「結果目標」(コンクールでの優勝など)、「パフォーマンス目標」(自分自身が最高のパフォーマンスを発揮すること)、「プロセス目標」(最高のパフォーマンスのために具体的に何をするかを設定する目標)があります。他人との比較や競争では、「勝てない」と思った時点で努力できなくなることもあります。自分の力でクリアしていける目標設定も大切です。
効果的な指導法
―――最後に、ピアノ教室などの教育現場で、効果的な指導法などについて教えてください。
生徒に合った目標設定を一緒に考えてあげることですね。一つの目標を達成したら、また次の目標を考える。その際には「PDCAサイクル」、つまりPlan(計画)→Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)の流れを考えるのも有効です。
そしてもう一つ大切なのは「自立性」です。生徒が選択したり、意見を言える環境を作ることです。すべてを指示するのではなく、例えば練習の順番を生徒に決めさせるなど、自分で選択する機会を与えることで「やらされている」感を持たずに、モチベーションが向上します。指導者はアドバイザーとして、生徒の考えを聞き、選択肢を提供してあげることが大切なのです。
—————
国際医療福祉大学大学院 副大学院長
国際医療福祉大学 精神医療統括教授
精神科〈精神医学(精神薬理学、認知行動療法、司法精神医学、社会精神医学、スポーツ精神医学など)〉
千葉大学名誉教授
千葉大学卒、医学博士
前千葉大学医学研究院精神医学教授/同大学医学部附属病院精神神経科長・こどものこころ診療部長/同大学社会精神医学教育研究センター長、元千葉大学大学院医学研究院副研究院長・副医学部長、元日本脳科学会理事長、元日本精神科救急学会会員、元厚生労働省社会保障審議会委員